【絶品】アイゴの美味しいおすすめの食べ方5選!アイゴは臭い?まずい?バリ、小さいアイゴの簡単で手軽なレシピ、調理法を解説!
磯釣りをしていると、よく釣れる魚のひとつに「アイゴ」がいます。背びれや腹びれに鋭い毒棘を持ち、さらに独特の磯臭さがあることから「まずい魚」「危険な魚」として敬遠されがちです。
しかし、実際にはアイゴはとても身がしっかりとした白身魚で、下処理と調理を正しく行えば驚くほど美味しく食べられます。特に新鮮な個体は旨味が強く、脂がのる季節には刺身や煮付けでも高級魚に引けを取らない味わいを楽しめます。
この記事では、まずアイゴの生態や特徴、釣ったあとの正しい下処理と注意点を解説し、そのうえで初心者でも簡単にできるおすすめの調理法を5つ紹介します。
「アイゴって本当に食べられるの?」「臭いが気になるけどどうすればいいの?」という疑問を持つ方にもわかりやすくまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください!!
アイゴとは?

アイゴはスズキ目アイゴ科に属する海水魚で、日本各地の沿岸部に広く生息しています。大きさは20〜30cmほどの個体が一般的で、群れを作って岩礁帯や海藻の多い場所に生息しているのが特徴です。体はずんぐりとした楕円形で、褐色や灰色がかった地味な体色をしており、あまり目立たない外見をしています。
一番の特徴は、背びれや腹びれ、尻びれにある鋭い毒棘です。この棘に刺されると激しい痛みと腫れを引き起こし、場合によっては数日間手が使えなくなるほど強力です。そのため、釣り人のあいだでは敬遠されがちな魚でもあります。
また、アイゴは主に海藻を食べる草食性の魚で、その食性が独特の磯臭さの原因になっています。アイゴが増えすぎると大量の海藻を食べ尽くしてしまい、「磯焼け」と呼ばれる現象が発生します。磯焼けは、海藻を餌にしているアワビやサザエといった貝類の減少を招き、海の生態系バランスを崩す大きな問題です。
そのため、一部の地域では「釣ったアイゴは持ち帰って食べる」ことが推奨されており、釣り人が資源管理に貢献できる魚でもあります。つまり、アイゴを美味しく食べることは単なる食の楽しみだけでなく、環境保全にもつながる行動なのです。
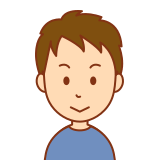
アイゴは、ヒレに毒があり敬遠されがちな魚ですが、適切なヒレの処理を行えばとても美味しく食べられる魚です。
アイゴについて更に詳しく解説した記事もありますので、ぜひ合わせてお読みください↓

アイゴは美味しいのか?

「アイゴは臭くてまずい」というイメージを持つ人が多いのは事実です。実際に、磯の海藻を多く食べているため、釣った直後の魚体には独特の匂いがあります。また、下処理を怠ると内臓から強い臭みが回り、せっかくの身の美味しさを損なってしまいます。
しかし、丁寧に処理されたアイゴは、実はとても美味しい白身魚です。身はしっかりと締まっていて歯ごたえが良く、クセのない上品な味わいがあります。旬の時期には脂ものり、煮付けや塩焼きにすると旨味が強く、刺身で食べればコリコリとした食感が楽しめます。特に秋から冬にかけては脂がのるため、最高の食材になります。
さらに、地域によっては高級魚として扱われることもあります。沖縄や奄美大島などでは「カーエー」と呼ばれ、人気の食用魚として親しまれています。つまり、「アイゴはまずい」というのは、正しく処理されていないアイゴを食べたときの印象であり、本来はポテンシャルの高い魚なのです。
アイゴ下処理と注意点

アイゴを美味しく食べるためには、釣った直後からの下処理がとても重要です。ここを怠ると「臭い魚」のイメージのままになってしまいます。
1. 毒棘の処理
アイゴの背びれ・腹びれ・尻びれには毒のある棘があります。この棘は非常に鋭く、うっかり刺さると強烈な痛みに襲われます。まず最初に、ハサミや包丁で棘を切り落としてから作業に入ることが安全です。釣り上げた時点でタオルやフィッシュグリップを使ってしっかりと魚を固定し、素手で触らないようにしましょう。
※アイゴの毒は死んだ後も残っています。釣り場にヒレを放置せずビニール袋に厳重に保管して持ち帰るようにしましょう。
アイゴの棘は硬いので、このような頑丈な魚バサミを使うことをおすすめします。こちらは、私筆者も愛用しているおすすめのものになります↓↓
2. 血抜きと内臓処理
アイゴの臭みの大きな原因は内臓にあります。釣ったらできるだけ早くエラを切り、尻穴から包丁を入れて血抜きを行います。その後、腹を割って内臓を丁寧に取り除きましょう。ここで素早く処理をするかどうかで、味が大きく変わります。また、アイゴは鱗がないので鱗取りの作業は不要です。
3. 鮮度管理
血抜きと内臓処理をしたら、氷水でしっかりと冷やして鮮度を保ちます。磯臭さは時間が経つほど強くなるので、持ち帰る際はクーラーボックスに氷をたっぷり入れて保存するのがポイントです。
このように、毒棘の処理と内臓処理、鮮度管理を徹底すれば、アイゴは格段に美味しくなります。
アイゴの棘の処理や、基本的な捌きかたをとても分かりやすく解説している動画がありましたので、こちらも参考にしてみてください↓
アイゴのおすすめの食べ方5選
ここでは、初心者でも手軽に楽しめるアイゴの絶品レシピを5つ紹介します。
刺し身

材料(2〜3人分)
- アイゴ(30〜40cm前後) … 1尾
- 氷水 … 適量
- 大葉やツマ … 適量
- わさび … 適量
- 醤油 … 適量
- ポン酢 … お好みで
作り方
- 釣った直後に処理する
釣り上げたらすぐにエラの付け根を切り、海水か真水で血抜きを行います。 その後、氷水に浸けて「氷締め」にすることで、臭みが抑えられ鮮度も長持ちします。 - ウロコと内臓を取り除く
家に持ち帰ったらすぐにウロコを取り、腹を割いて内臓を丁寧に取り除きます。 特に腸の部分に臭みが強く出るため、流水でしっかり洗い流すのが重要です。 - 三枚におろす
頭を落とし、背骨に沿って包丁を入れて三枚におろします。 腹骨を薄くすき取り、血合い骨は骨抜きで取り除きます。 - 皮を引く
アイゴの皮は硬めなので、尾の方から包丁を寝かせて丁寧に皮を引きます。 この工程で身の透明感が出て、刺し身らしい仕上がりになります。 - 刺し身に切る
サクに整えたら、包丁を斜めに引いて薄造りにします。 器に大葉やツマを添えて盛り付けると、見た目も美しくなります。 - 食べ方
わさび醤油はもちろん、ポン酢に柚子やすだちを搾って食べると爽やかさが増し、磯臭さが気になりません。
ポイント
アイゴの刺し身を美味しく食べるための最大のコツは「釣った直後の処理」と「内臓・血合いの徹底除去」です。 ここを怠ると臭みが強くなってしまうため注意してください。 また、皮を引いたあとの身を一度ペーパーで軽く拭き取り、冷蔵庫で少し寝かせると、 水分が落ち着いて旨みがより引き立ちます。
アイゴの干物

アイゴはそのままだと独特の磯臭さが気になる魚ですが、干物に加工すると水分が抜けて旨みが凝縮され、 香ばしく食べやすい味わいになります。特に釣ったその日に処理して干せば、鮮度の良さを活かした絶品の干物に仕上がります。干物は、アイゴの定番料理として知られているので、ぜひ一度作ってみてください!!
材料(2〜3枚分)
- アイゴ(30cm前後) … 2〜3尾
- 塩 … 大さじ3
- 水 … 1リットル
- 酒 … 大さじ2(臭み消し用)
作り方
- 下処理
釣ったらすぐに血抜きを行い、氷締めして持ち帰ります。 家に帰ったらウロコを取り、内臓を丁寧に除去し、腹の中をよく洗って血を残さないようにします。 - 開きにする
背開きまたは腹開きにして、背骨を残したまま両側に開きます。 水気をキッチンペーパーで拭き取ります。 - 塩水に漬ける
水1リットルに対して塩大さじ3と酒大さじ2を加えてよく溶かします。 この塩水にアイゴを30分〜1時間ほど浸け、臭みを抜きつつ下味をつけます。 - 干す
漬け終わったら取り出して水気を切り、風通しの良い日陰で半日〜1日干します。 しっかり干すと保存性が高まり、軽く干せばふっくらした食感が楽しめます。 - 焼く
食べる際はグリルや炭火で両面を香ばしく焼き上げます。 焼きすぎると身が硬くなるので、中まで温まったらすぐに火を止めるのがポイントです。
ポイント
干物にすることでアイゴ特有の臭みが大幅に和らぎ、旨みが凝縮されます。 一夜干しなら柔らかくジューシーに、しっかり干せば保存食としても優秀です。 焼き上がりにレモンを絞ったり、大根おろしを添えるとさらに食べやすくなります。
アイゴの唐揚げ

アイゴは独特の磯臭さがある魚ですが、唐揚げにすると香ばしさが際立ち、 外はカリッと、中はふっくらとした食感に仕上がります。 小型のアイゴなら丸ごと、中型以上ならぶつ切りにして揚げると食べやすくなります。また、臭みのある個体でも、濃い味付けにすれば匂いも気にならないため失敗がなくおすすめです。
材料(2〜3人分)
- アイゴ(中型) … 1〜2尾
- 醤油 … 大さじ2
- 酒 … 大さじ1
- 生姜(すりおろし) … 小さじ1
- にんにく(すりおろし) … 小さじ1
- 片栗粉 … 適量
- 揚げ油 … 適量
- レモン … お好みで
作り方
- 下処理
釣ったらすぐに血抜きをして氷締めします。 家に帰ったらウロコ・内臓をしっかり取り、食べやすい大きさにぶつ切りにします。 - 下味をつける
ボウルに醤油・酒・生姜・にんにくを入れて混ぜ、切ったアイゴを20〜30分漬け込みます。 こうすることで臭みが抜け、味もしっかり染み込みます。 - 粉をまぶす
下味をつけたアイゴの水分を軽く拭き取り、片栗粉を全体に薄くまぶします。 衣は薄めにするとカリッと仕上がります。 - 揚げる
170℃前後に熱した油で、表面がカリッとするまで4〜5分揚げます。 大きめの切り身は二度揚げすると中までしっかり火が通り、骨も食べやすくなります。 - 仕上げ
揚げたてを皿に盛り付け、レモンを搾っていただきます。 ビールのお供やご飯のおかずにぴったりです。
ポイント
唐揚げはアイゴ特有の臭みを和らげる調理法の一つです。 下味に生姜やにんにくを加えると、さらに食べやすくなります。
骨まで揚げれば「骨せんべい」として楽しめるので、無駄なく美味しく味わえます。
アイゴのフライ

アイゴをフライにすると、外はサクサク、中はふんわりとした食感になり、 子どもから大人まで食べやすい料理になります。下処理をしっかり行えば、 磯臭さもほとんど気にならず、家庭で簡単に楽しめます。
材料(2〜3人分)
- アイゴ(中型) … 1尾
- 小麦粉 … 適量
- 卵 … 1個
- パン粉 … 適量
- 塩・こしょう … 少々
- 揚げ油 … 適量
- レモン … お好みで
- タルタルソース … お好みで
作り方
- 下処理
釣ったらすぐに血抜きと氷締めを行い、ウロコと内臓を取り除きます。 三枚におろし、骨を取り除いた身をフライ用に切ります。 - 下味をつける
切った身に塩・こしょうを軽くふり、下味をなじませます。 10分ほど置くと味がしっかりします。 - 衣をつける
身に小麦粉を薄くまぶし、溶き卵にくぐらせてからパン粉をつけます。 衣は薄めにするとサクッと仕上がります。 - 揚げる
170℃前後の油で、きつね色になるまで約3〜4分揚げます。 大きめの切り身は二度揚げするとよりサクッと仕上がります。 - 仕上げ
揚げたてを皿に盛り付け、レモンやタルタルソースを添えていただきます。 衣の香ばしさとアイゴのふんわりした身が絶妙にマッチします。
ポイント
フライにする際は衣を薄めにすると、魚本来の味を楽しめます。 下味に塩・こしょうやレモン汁を少量加えることで、磯臭さがさらに抑えられます。
小骨が気になる場合は骨抜きで丁寧に取り除くと食べやすくなります。
アイゴの漬け

新鮮なアイゴの身を醤油ベースのタレに漬け込むことで、旨味がしっかり染み込み、 クセが少なく食べやすい一品になります。ご飯と一緒に食べると絶品で、丼にしてもおすすめです。
材料(2〜3人分)
- アイゴ(刺し身用に処理したもの) … 1尾分
- 醤油 … 50ml
- みりん … 25ml
- 酒 … 25ml
- 砂糖 … 小さじ1
- 生姜(すりおろし) … 小さじ1
- 青ネギや大葉(飾り用) … 適量
- ご飯 … 適量(丼にする場合)
作り方
- 下処理
アイゴは釣ったらすぐに血抜きと氷締めを行い、ウロコ・内臓を取り除きます。 三枚におろし、腹骨や血合い骨を取り除き、刺し身用に柵取りします。 - 漬けダレを作る
醤油、みりん、酒、砂糖、生姜を小鍋でひと煮立ちさせ、粗熱を取ります。 このタレを使ってアイゴの身を漬け込みます。 - 漬け込む
容器に刺し身を入れ、タレをかぶる程度に注ぎます。 冷蔵庫で30分〜1時間漬け込むと、程よく味が染み込みます。 - 盛り付け
漬けたアイゴを器に盛り付け、青ネギや大葉を添えます。 ご飯の上にのせて丼にするのもおすすめです。 - 食べる直前に
タレを少量かけて食べると、さらに味わい深くなります。 お好みで刻み海苔やわさびを添えても美味しいです。
ポイント
漬けにする際は、漬け込みすぎると身が硬くなったり味が濃くなりすぎるので注意してください。
新鮮なアイゴを使うことが美味しい漬けを作る最大のコツです。 また、タレに生姜を加えることで磯臭さを抑え、より食べやすくなります。
まとめ

アイゴは「臭い」「まずい」と思われがちな魚ですが、実際には正しい下処理と調理をすれば非常に美味しく食べられる魚です。鋭い毒棘や独特の磯臭さといった特徴から敬遠されることが多いものの、それらは正しい知識と工夫で解決できます。
さらに、アイゴは磯焼けという海の環境問題の要因にもなっており、釣って持ち帰り食べることは資源保全にもつながります。つまり、アイゴを料理して食べることは「美味しくいただく」だけでなく、「環境に優しい選択」にもなるのです。
ぜひこの記事を参考にして、アイゴ料理に挑戦してみてください。新しい魚の美味しさを発見できるはずです。
関連記事はこちらから!!



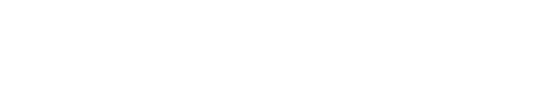

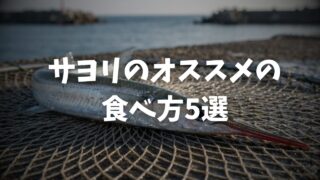


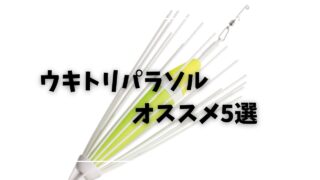


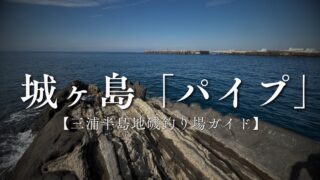


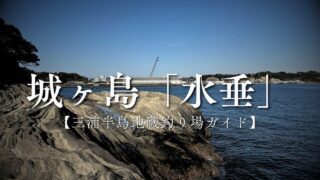










コメント